【サービス業】経理の丸投げで本業に専念することが可能に!


☑経理担当者の退職で会社に起こり得るトラブルを把握したい。
☑経理担当者が突然退職した場合の対応方法を知りたい
☑経理業務の属人化を防ぎ、突然の退職リスクを最小化する仕組みを整えたい。
経理担当者が突然退職すると、会社の業務は一気に慌ただしくなります。請求や支払い、給与計算など、日々の経理業務が止まってしまい、「どうしよう…」と焦る場面も少なくありません。このコラムでは、そんな緊急事態にどう対応すればよいのか、そして今後に備えてどんな準備ができるのかを、わかりやすく解説していきます。
目次

経理担当者が退職したとき、企業の業務にはどんな影響があるのでしょうか。実際に起こり得る課題を、以下に整理しています。
経理担当者の突然の退職は、支払いや請求業務の滞りにつながるリスクがあります。請求漏れや支払い遅延は、取引先との信用問題に直結するため注意が必要です。まずは未処理の請求書や支払予定を洗い出し、優先順位をつけて対応しましょう。
経理業務が滞ることにより、経費精算や給与計算が遅れると、社員の不満やモチベーション低下につながる恐れがあります。特に給与は生活に直結するため、遅延は信頼を損なう大きな要因になります。まずは締め日や支払日などのスケジュールを把握し、対応の緊急度が高い業務から順に取り組むことが大切です。
経理業務の引継ができていないと、税務申告や決算対応に大きな混乱が生じる可能性があります。申告期限や決算スケジュールは厳守が求められるため、対応が遅れると罰則や信用低下につながるおそれがあります。まずは必要な書類や処理状況を確認し、期限までに対応できる体制を整えることが重要です。
請求や支払いが滞ることで、取引先からの信頼を損なう恐れがあります。支払期日の遅延や請求書の不備は、相手先に不安や不信感を与え、今後の取引に影響を及ぼすこともあります。まずは未処理の取引状況を整理し、誠実かつ迅速な対応を心がけることが大切です。必要に応じて、事情を説明したうえで柔軟な調整をお願いすることも検討しましょう。
経理業務が特定の担当者に依存していると、その担当者が退職する際に円滑な引き継ぎが難しくなります。特に、業務内容や処理手順が口頭伝達や個人メモに頼っている場合、情報の共有が不十分となり、残された社員に過度な負担がかかる恐れがあります。

経理担当者の退職は組織にとって重大なリスクです。不可欠な業務が滞れば資金繰りや決算に直結し、経営全体へ影響しかねません。だからこそ迅速な初動と中長期的な体制整備が必要です。
経理担当者が退職した際は、まず現状を正確に把握することが重要です。業務の棚卸しを行い、どの業務が滞っているかを洗い出し、優先順位をつけて対応方針を整理します。次に、関係部署や経営陣など社内関係者に状況を周知し、今後の対応策を共有します。業務が逼迫している場合は、税理士や会計事務所など外部の専門家に一時的に業務を依頼することも検討しましょう。また、社内の他部署から一時的に人員を再配置することで、急場をしのぐ体制を整えることも有効です。
今後の業務継続性と組織力強化を見据え、以下の中長期的な対応策を講じることが重要です。
業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の品質で遂行できるよう、業務手順や留意点を明文化し、マニュアルとして体系的に整備します。これにより、担当者の交代時にも円滑な引き継ぎが可能となり、業務の継続性と安定運用を支える基盤が整います。
これまで紙やローカル環境で管理されてきた経理業務も、クラウド化の波に乗って大きく変化しています。リアルタイムでの情報共有やリモート対応が可能になり、業務のスピードと柔軟性が格段に向上しました。
クラウド化は、単なるツールの導入ではなく、経理の働き方そのものをアップデートする取り組みです。ペーパーレス化とあわせて進めることで、業務の効率化だけでなく、セキュリティや継続性の面でも大きなメリットが期待できます。
最近では、経理代行サービスを活用する企業が増えてきました。日々の記帳や給与計算など、定型的な業務を外部に委託することで、社内の負担を軽減し、コア業務に集中できる環境づくりが進んでいます。
経理代行サービスは、経理業務のプロフェッショナルによる支援が受けられる一方で、その品質にはばらつきがあるのも事実です。だからこそ、信頼できるパートナーを見極める目が重要になります。単に「安いから」ではなく、コストと品質のバランスを見極めながら、必要な部分に外部の知見を取り入れることが、業務の安定性と精度を高める鍵となります。
アウトソーシングは、弱みを補うための手段ではなく、組織の強みを最大化するための戦略的なパートナーシップです。柔軟な運用体制の構築に向けて、前向きに検討したい選択肢のひとつです。
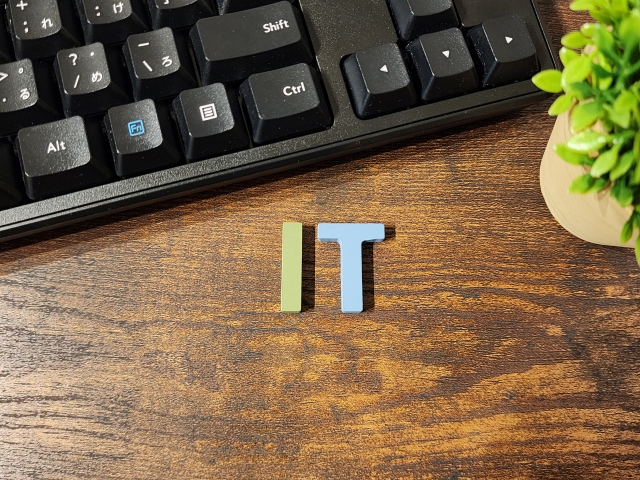 K社は、従業員約30名のIT企業です。創業以来10年間、経理業務を担っていた専任担当者が、家族の転居を理由に急遽退職することになりました。引き継ぎの時間も十分に確保できなかったため、急きょ総務担当者が経理業務を兼任することになりましたが、経理の知識や経験が乏しく、業務は混乱しました。
K社は、従業員約30名のIT企業です。創業以来10年間、経理業務を担っていた専任担当者が、家族の転居を理由に急遽退職することになりました。引き継ぎの時間も十分に確保できなかったため、急きょ総務担当者が経理業務を兼任することになりましたが、経理の知識や経験が乏しく、業務は混乱しました。
書類は紙ベースで保管されており、ファイリングはされていたものの、必要な資料を探すのに時間がかかり、業務効率が大きく低下しました。さらに、経費精算の遅れによって振込ミスが発生し、社員の不満が高まったことで、社内の雰囲気にも悪影響が出始めました。
このような状況を受けて、同社の代表から弊社にご相談をいただきました。弊社では、まずペーパーレス化の推進とクラウド会計ソフトの導入をご提案しました。総務担当者が経理代行サービスの窓口を務める体制を整えたことで、日々の記帳や給与計算などのルーチン業務をアウトソーシングできるようになり、業務負荷を大幅に軽減することができました。
また、確定申告まで一貫して依頼したいというご要望を受け、弊社に在籍する税理士が対応しました。申告業務は税理士の独占業務であり、税理士が不在の経理代行会社が対応することは法律上認められていませんが、弊社では適切な体制のもとで対応が可能です。
その結果、業務の属人化を解消し、社内での情報共有も円滑に進むようになりました。経理体制の再構築を通じて、社員の安心感と業務の安定性を取り戻すことができました。
>関連コラムはこちら『経理代行が税理士法違反になるのか?ケースごとに徹底解説』
経理担当者が急に辞めたとき、よくある質問とその対応ポイントをご紹介します。
経理業務の属人化を防ぐためには、業務の再構築に向けた社内準備が欠かせません。まずは業務フローを可視化し、必要な書類やデータを整理しましょう。次に、誰が担当しても対応できるよう業務マニュアルを整備します。さらに、クラウド会計ソフトの導入も有効です。IDとパスワードがあれば複数の端末からアクセスでき、情報共有が容易になるため、業務のブラックボックス化を防げます。これにより、担当者が急に退職しても業務が滞るリスクを最小限に抑えられます。
>関連コラムはこちら『【税理士事務所が解説】最近よく聞くクラウド会計とは?メリット・デメリットを解説』
経理担当者の退職後、正社員の再採用・派遣社員の活用・経理代行の利用のいずれを選ぶかは、企業の状況によって異なります。
・正社員の採用:長期的な安定が期待できますが、採用コストや教育費、固定給がかかります。
・派遣社員の活用:即戦力として有効ですが、手数料やスキルのばらつきに注意が必要です。
・経理代行サービス:業務量に応じて柔軟に依頼でき、経験豊富なプロによる安定した対応が可能です。
即戦力と安定性を重視するなら、経理代行サービスの活用は有力な選択肢といえるでしょう。
>関連コラムはこちら『【税理士事務所が解説】最近よく聞くクラウド会計とは?メリット・デメリットを解説』
経理代行サービスを選ぶ際は、導入時のサポート体制が整っているかを確認することが大切です。また、実績や導入経験が豊富かどうかも信頼性を見極めるポイントになります。加えて、会計データを扱う以上、セキュリティ対策が十分に講じられているかも重要です。申告業務まで依頼したい場合は、税理士が常駐している事業者を選ぶと安心ですし、クラウド会計ソフトの導入支援があるかどうかも、業務効率化の観点からチェックしておきたい点です。
>関連コラムはこちら『経理アウトソーシングで失敗しない!業者選びのコツ5選』
日本橋経理代行は、母体となる税理士事務所サイバークルー株式会社であるため、日々の経理業務の代行から決算申告まで幅広く承っています。さらに、弊社へのご依頼をきっかけに、近年広まっているクラウド会計を導入された企業様の実績も多数ございます。「自社に最適な節税対策を知りたい。」「経理業務の効率化を図りたい…。」「クラウドを導入したいがどうしたら良いかわからない…。」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!
税理士と経理代行のご契約は別の契約となりますので、既に他の税理士さんとご契約いただいている場合でも、経理代行サービスのみのご利用も可能です。
まずは中央区日本橋経理代行サービス無料相談をご活用ください。こちらよりサービス内容の詳細と料金表もご確認いただけます。



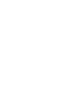
経理を楽に、シンプルに
バックオフィス業務の専門家である弊社のスタッフが現状の煩雑な経理・労務体制を解決するための最適な提案を実施いたします!


間接部門のコストカットを実現
経理担当者の人件費に加え、専門家を活用することによる採用・育成コストも削減できます!


経営のスピードアップを実現!
業務フローの見直し&クラウド型バックオフィス管理システムの活用でリアルタイムでの経営数値を把握&スピーディな経営判断を実現します。


高品質&親身なバックオフィスサポート
多数の経理・労務を改善してきた専門家が中小企業のバックオフィス体制の見直し&アウトソーシングを親身にサポートさせていただきます!
中小企業の経理を徹底改善
経理のサポートに特化した実績
「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています
